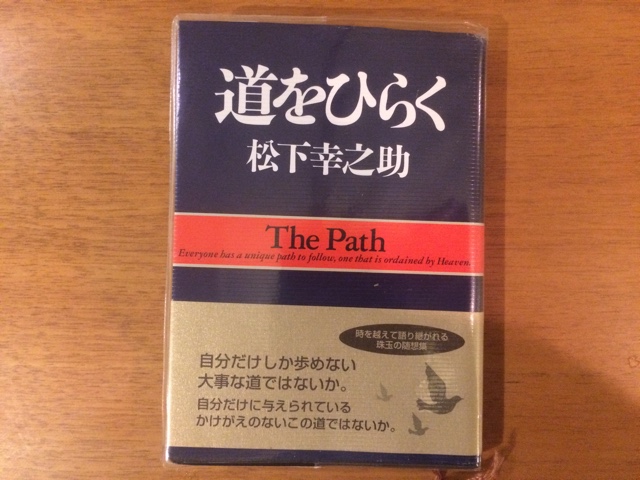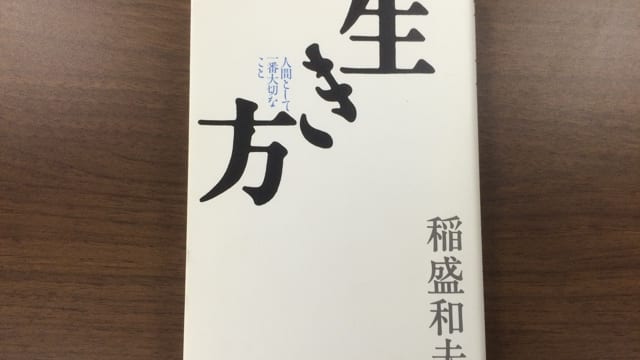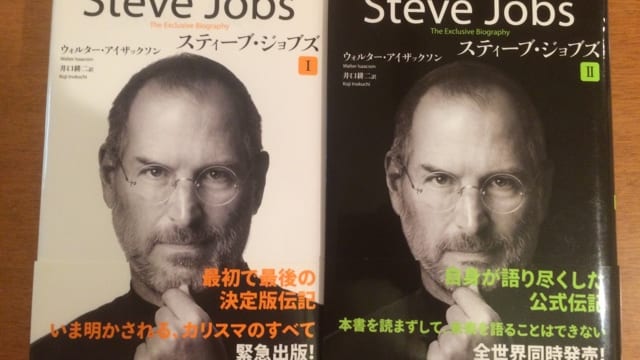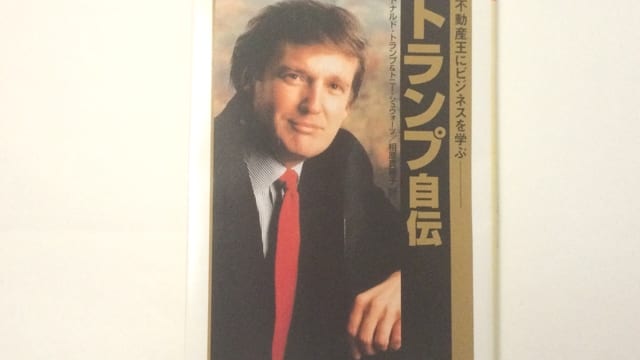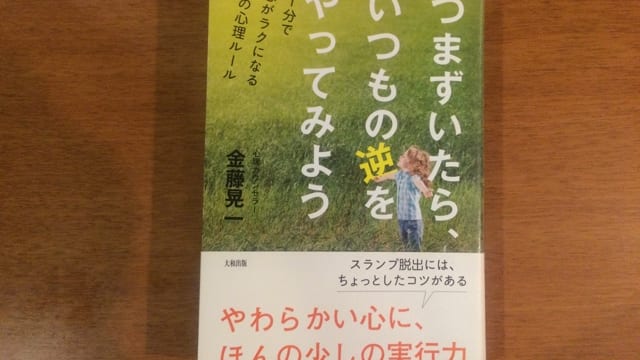松下幸之助さんの「道をひらく」を読んだので、学んだことを中心にまとめ、感想もお伝えします。
もくじ
- 1 要約と感想
- 1.1 道
- 1.2 素直に生きる
- 1.3 手さぐりの人生
- 1.4 若葉の峠
- 1.5 生と死
- 1.6 日々是新(ひびこれあらた)
- 1.7 心の鏡
- 1.8 雨が降れば
- 1.9 日に三転す
- 1.10 花のように
- 1.11 くふうする生活
- 1.12 長所と短所
- 1.13 断を下す
- 1.14 善かれと思って
- 1.15 止めを刺す
- 1.16 世の宝
- 1.17 自問自答
- 1.18 思い悩む
- 1.19 時を待つ心
- 1.20 仕事というものは
- 1.21 転んでも
- 1.22 紙一重
- 1.23 絶対の確信
- 1.24 一人の知恵
- 1.25 旗を見る
- 1.26 見方を変える
- 1.27 商売の尊さ
- 1.28 手を合わす
- 1.29 あぶない話
- 1.30 熱意をもって
- 1.31 同じ金でも
- 1.32 虫のいいこと
- 1.33 恵まれている
- 1.34 あぐらをかく
- 1.35 後生大事
- 1.36 身にしみる
- 1.37 正常心
- 1.38 もっとも平凡な
- 1.39 年の瀬
- 1.40 知恵の幅
- 1.41 まねる
- 1.42 わけ入れば
- 1.43 談笑のうちに
- 1.44 求めずして
- 1.45 ダムの心得
- 2 電子書籍とオーディオブックはある?
要約と感想
黄色い枠が私の感想です。
道
この道が果たしてよいのか悪いのか、思案にあまる時もあろう。
いま立っているこの道、いま歩んでいるこの道、ともかくもこの道をあゆむことである。自分だけしか歩めない大事な道ではないか。自分だけに与えられているかけがえのないこの道ではないか。
それがたとえ遠い道のように思えても、休まず歩む姿からは必ず新たな道がひらけてくる。深い喜びも生まれてくる。
素直に生きる
素直さを失ったとき、逆境は卑屈を生み、順境は自惚れを生む。
素直さは人を強く正しく聡明にする。逆境に素直に生き抜いて来た人、順境に素直に伸びてきた人、その道程は異なっても、同じ強さと正しさと聡明さを持つ。
手さぐりの人生
わからない人生を、わかったようなつもりで歩むことほど危険なことをはない。わからない世の中を、みんなに教えられ、みんなに手を引かれつつ、一歩一歩踏みしめて行くことである。謙虚に、そして真剣に。おたがいに人生を手さぐりのつもりで歩んでゆきたいものである。
若葉の峠
峠から峠に移る旅路かな
避けられなければ、やはりただ懸命に歩むほかないであろう。
それでも元気に懸命に、超えられるだけの峠を超え、歩めるだけの旅路を歩みたい。
生と死
死を恐れるよりも、死の準備のないことを恐れたほうがいい。
与えられている生命を最大に生かさなければならないのである。それを考えるのが死の準備である。そしてそれが生の準備となるのである。
日々是新(ひびこれあらた)
きのうはきのう、きょうはきょう。きのうの苦労はきょうまで持ち越すことはない。「一日の苦労は一日にて足れり」というように、きょうはまたきょうの運命がひらける。きのうの分まで背負ってはいられない。毎日が新しく、毎日が門出である。
心の鏡
人はとかく、自分の考えやふるまいの誤りが自覚しにくい。心の鏡がないのだから、ムリもないといえばそれまでだが、けれど求める心、謙虚なこころさえあれば、心の鏡は随処にある。
自分の周囲にある物、いる人、これすべて、わが心の反映である。
スポンサーリンク
雨が降れば
治にいて乱を忘れず
ただ、雨があがるのを待って、二度と再び雨に濡れない用意だけはこころがけたい。
日に三転す
古人は「君子は日に三転す」と教えた。一日に三度も考えが変わるということは、すなわちそれだけ新たなものを見いだし、生み出しているからこそで、これこそ君子なりというわけである。
花のように
せめてわれわれだけでも、清らかな泉のように、毅然たる一輪の花のように、強く正しく働いてゆこうではないか。
どんな世の中になっても、あわてず、うろたえず、淡々として社会への奉仕をこころがけてゆこう。その姿自体が、人々によってすでに大きな励ましとなり、憩いとなるのである。
くふうする生活
失敗することを恐るよりも、生活にくふうのないことを恐れた方がいい。
きのうと同じことをきょうは繰り返すまい。どんな小さなことでもいい。どんなわずかなことでもいい。
多くのひとびとの、このわずかなくふうの累積が、大きな繁栄を生み出すのである。
長所と短所
神さまではないのだから、全知全能を人間に求めるのは愚の限りである。人に求めるほうも愚なら、いささかのうぬぼれに自ら心おごる姿も、また愚である。人を助けて己の仕事が成り立ち、また人に助けられて己の仕事が円滑に運んでいるのである。この理解と心くばりがなければ、百万の人も単につのつき合わした烏合の衆にすぎないであろう。
断を下す
進むもよし、とどまるもよし。要はまず断を下すことである。みずから断を下すことである。
断を下さないことが、自他共に好ましくないことだけは明らかである。
善かれと思って
善意の策も悪意の策も、策は所詮策にすぎない。
何事においても策なしというのがいちばんいいのである。
無策の策といってしまえば平凡だけれども、策なしということの真意を正しく体得して、はからいを超え、思いを超えて、それを自然の姿でふるまいにあらわすには、それだけのいわば悟りと修練がいるのではなかろうか。
止めを刺す
せっかくの99パーセントの貴重な成果も、残りの1パーセントの止めがしっかりとさされていなかったら、それは初めから無きに等しい。
世の宝
昔の武将が、攻められる前に、秘蔵の名器を城外に出したエピソード。
スポンサーリンク
自問自答
だがしかし、やっぱり大事なことは、他人の評価もさることながら、まず自分で自分を評価するということである。自分のしたことが、本当に正しかったかどうか。その考え、そのふるまいにほんとうに誤りがなかったかどうか、素直に正しく自己評価するということである。
そのためには、素直な自問自答を、くりかえし行わねばならない。みずからにといつつ、みずから答える。これは決して容易ではない。安易な心が目で、できることではないのである。しかし、そこから真の勇気がわく。真の知恵もわいてくる。
思い悩む
わからなければ、人に聞くことである。己のカラに閉じこもらないで、素直に謙虚に人の教えに耳を傾けることである。それがどんな意見であっても、求める心が切ならば、そのなかから、おのずから得るものがあるはずである。
時を待つ心
時を得ぬ人は静かに待つがよい。大自然の恵を心から信じ、時の来るを信じて、着々とわが力をたくわえるがよい。着々とわが力をたくわえる人には、時は必ず来る。時期は必ず来る。
仕事というものは
勝負する大勇気をもって仕事にあたらねば、それこそ真の繁栄は生まれないであろう。
仕事を勝負と心得る人と心得ない人とのちがいが、ハッキリとあらわれてくるときではなかろうか。
転んでも
一度転んで気がつかなければ、七度転んでも同じこと。一度で気のつく人間になりたい。
そのためには「転んでもただ起きぬ」心がまえが大切。
失敗することを恐れるよりも、真剣でないことを恐れたほうがいい。真剣ならば、たとえ失敗しても、ただは起きぬだけの充分な心がまえができてくる。
紙一重
紙一重のものの見方のーちがいから、賢と愚、成功と失敗、繁栄と貧困の別がうまれてくるのであるから、やはりいいかげんに、ものの見方をきめるわけにはゆくまい。
素直に見るか見ないか、ここに紙一重の鍵がひそんでいる。
絶対の確信
神か仏でないかぎり、絶対に間違いのない道など、ほんとうはないのである。だからこそ、おたがい過ちすくなく歩むために、あれこれと思い悩み、精一杯に考える。その果てに、どうにもほかに道がなさそうで、だからこの道がいちばんよさそうで、そう考えて、それでもまだ心もとないけれども、こころもとないままではしかたがないから、そこに勇気をふるってあゆみつづけるのである。みずからを励まし励ましあゆみつづけるのである。
一人の知恵
他人に迷惑をかけるくらいなら、一人の知恵で歩まぬほうがいい。
たとえわかっていると思うことでも、もう一度、人にきいてみることである。
「見ること博ければ迷わず。聴くこと聡ければ惑わず」という古言がある。相手がどんな人であろうと、こちらに謙虚な気持ちがあるならば、思わぬ知恵が与えられる。
旗を見る
その中には、たとえば数字という形で、目にみえてくるものもある。しかし、目に見えない旗のほうがはるかに多いであろう。
その見えない旗をみきわめて、毎日の成果を慎重に検討してゆくところに、仕事の真の成長があり、毎日の尊い累積がある。
目に見えない旗をも、よく見きわめるだけの心がけを、つねにきびしく養っておきたいものである。
スポンサーリンク
見方を変える
案外、人は無意識の中にも一つの見方に執して、他の見方のあることを忘れがちである。そしてゆきづまったと言う。ゆきづまらないまでもムリをしている。貧困はこんなところから生まれる。
われわれはもっと自在でありたい。自在にものの見方を変える心の広さを持ちたい。何事も一つに執すれば言行公正を欠く。深刻な顔をする前に、ちょっと視野を変えてみるがよい。それで悪ければ、また見方を変えればよい。そのうちに、本当に正しい道がわかってくる。模索のほんとうの意味はここにある。
素直や無策の策と同じく、あまり固執せずに、ひらひらと自在に自分の見方を変えることが大事なんだと思った。このあたりは仏教っぽい考え方だと思う。自然と自分は一体であり、自然に即して生きる、みたいな。禅などを通して、このような素直な心が体得できるのでは、と思ったりする。
ただ、「自分の道を歩む」というのと少し矛盾する気がする。自在に道を変えてしまったら、違う道を行ってしまう恐れがあるのでは。
商売の尊さ
宗教の力は偉大である。人びとを救うという強い信念のもとに、世間の求めるものを進んで与えてゆく。
商売というものも、この宗教に一脈相通ずるものがあるのではなかろうか。商売というものは、暮らしを高め、日々を豊かに便利にするために、世間の人が求めているものを、精いっぱいのサービスをこめて提供してゆくのである。だからこそ、それが不当な値段でないかぎり、人びとに喜んで受け入れられ、それにふさわしい報酬も得られるはずである。
それを、こころならずも値切られて、正当な報酬もえられないままに苦しむということであれば、これははたしてどこに原因があるのであろう。
手を合わす
客が食べ終わって出て行く後ろ姿に、しんそこ、ありがたく手を合わせて拝むような心持ち、そんな心持ちのうどん屋さんは、必ず成功するのである。
手を合わせて拝む、と言う行為自体が成功に直接つながるのではなく、そのような心持ちで働くということは、その他のことにも気がつき改善していくから成功する、と言うことだと思う。
アフィリエイトで「手を合わす」行為とはなんだろう。一人一人の読者の顔を想像して「読ん頂きありがとうございます。」ということを言うことだろうか。それとも、文章の一言一言を丁寧に考えることか、儲かるからといって不要なものをオススメしないことか。
あぶない話
だが、人間というものは、なかなかそうはゆかない。ちょっとの成功にも、たやすく絶対の確信を持ちたがる。
だから、どんなえらい人でも、三度に一度は失敗したほうが身のためになりそうである。そしてその失敗を、謙虚さにうまれかわらせたほうが、人間が伸びる。
熱意をもって
何としても二階に上がりたい。どうしても二階に上がろう。この熱意がハシゴを思いつかす。階段をつくりあげる。上がっても上がらなくても…そう考えている人の頭からは、ハシゴは出てこない。
才能がハシゴをつくるのではない。やはり熱意である。
熱意には賛同する。ただ、いきなり最上階を目指してしてしまうと、ちょっとの挫折でモチベーションがガタ落ちしてしまう恐れがあると思う。だから、ここで「二階」となっているのだと思う。次のステージに集中する、それがコツだと思う。そして、何が二階かを考えることが大事で、センスと経験が必要なんだと思う。
この「二階」は最初に出てきた「峠」と似ていると思う。二階に登れば次は三階が見えて来る。一個一個登って行くうちに、最上階に近づいて行く。それを一個ずつ楽しみながら登って行く、そういう気持ちが大事と、松下さんは言っているんだと思った。
同じ金でも
同じ金でも、他人からポンともらった金ならば、ついつい気軽に使ってしまって、いつの間にか雲散霧消。金がいきない。金の値打ちも光らない。
金は天下のまわりもの。自分の金といっても、たまたまその時、自分が持っているというだけで、所詮は天下国家の金である。その金を値打ちもなしに使うということは、いわば天下国家の財宝を意義なく失ったに等しい。
金の値打ちを生かして使うということは、国家社会にたいするお互い社会人の一つの大きな責任である。義務である。そのためには、金はやはり、自分のアセ水をたらして、自分の働きでもうけねばならぬ。自分のヒタイのアセがにじみ出てないような金は、もらってはならぬ、借りてはならぬ。
まず、公のために働くべき、という前提がある。国家のお金を自分ごとのように使うためには、自分で苦労してかせがないといけない、ということだと思った。
もしかしたら、自己資金でビジネスをしていても、公から出資してもらているという感覚を持ったほうがいいのかもしれない。
逆に、自分ごとのように考えるためには、アセをかくことが必須なんだろうか、と思う。その辺で会った人のことを自分ごとのように考えるのは難しいということだろうか。
また、どこかで、「額にアセのない涼しい姿も称えるべきであろう」って書いてたけど、工夫して稼いだお金についてはどうなんだろう、と思った。
虫のいいこと
傘も持たないで自分だけはぬれないような虫のいいことを考えているならば、やがではどこかでつまずく。
やはり虫のいいことは、なるべく考えないほうがいい。
ときには静かに、自分の言動を自然の理に照らして、はたして虫のいいことを考えていないかどうかを反省してみたいものである。
自然の理を受け入れることと、素直や無策の策にも共通しているような現実を受け入れることと近い気がした。
自然の理を見ていないケースは2パターンある気がする。
一つ目は、それについての情報は得ているのに、直視したくないもの。
二つ目は、まだ情報も得ていないので、これからなんらかの手段で得て行くもの。
素直や無策の策は一つ目のことで、今回の自然の理は二つめのことを言っている気がする。
恵まれている
せっかく恵まれた自分の境遇も、これを自覚しないままに、いつのまにか自分の手でこわしてしまいがちである。
恵みにたいして感謝をし、その感謝の心で生き生きと働いたならば、次々とよい知恵も生れて、自他ともにどんなしあわせな暮らしができることか、思えば愚かなことである。
おたがい修行をしよう。自分は恵まれているということを、直接、自分の心にひびかすために、日常の立居振舞に、今一度反省を加えてみよう。
あぐらをかく
人それぞれの地位や役割というものは、それぞれに担当している仕事を、周囲の人びとと相協力して、よりすみやかに、より高く進歩させ充実させてゆくことによって、社会の発展、人みなの繁栄に資するために与えられているのである。そんなところであぐらをかいて、いいはずがない。
スポンサーリンク
後生大事
一方に「バカの一つ覚え」といわれるぐらいに仕事に熱心な人もいる。こう言う人は、やはり仕事に一心不乱である。つまらないと見える仕事も、この人にとっては、いわば後生大事な仕事、それに全身全霊を打ちこんで精進する。しぜん、その人の持てる知識は最上の形で働いて、それが仕事のうえに生きてくる。成功は、そこから生まれるという場合が非常に多い。
仕事が成功するかしないかは第二のこと。要は仕事に没入することである。一心不乱になることである。そして後生大事にこの仕事に打ち込むことである。そこから、ものがうまれずして、いったいどこから生まれよう。
身にしみる
今日、小さなビル一つを建てるのに、文明の利器をフルに利用しても、一年半はかかる。ところが、あの豪壮華麗な大阪城が、諸事不便なあの時代に、わずか一年半で築造されたという。その大業の根底には、築造に従事した人びとに、へたをすれば首を切られる、やり通さなければ首がとぶという生命をかけた真剣さがあったのである。そのことのよしあしは別として、生命を失うかもしれないということほど、身にしみるものはない。
正常心
わが国の人心は、現在、はたして正常にかえったかどうか。生活は正常にかえったのに、”非常”に甘えたふるまいや考え方が、なお根強く残っていはしないか。
正常心にかえるためには大きな勇気がいる。勇気を持って反省してみたい。ふりかえってみたい。そこに人としての道のはじまりがあるといえよう。
もっとも平凡な
それもこれも、つまりは自分なりの都合のよい道を求めてのことであろうけれども、自他ともの真の繁栄への道は、本当はもっとも平凡なところにある。みんなが納得するしごくあたりまえのところにある。別にむつかしく考える必要はないのではないか。
自然の理にかえって、もう一度素直な心で考え直してみたい。
ビジネスでは、みんながやることの逆を行け、という考え方がある。それとはちょっと相いれないのではないかと思った。
また、大衆には愚かな面もある。みんなが納得すると考えていたら、自分もおろかな道を行くことになりはしないか。
年の瀬
年の瀬は、これを越してしまえば年の始めがある。しかし生命の瀬はそれでおしまい。まことに融通のきかない話である。
しかし融通がきかないからこそ、人はまた真剣にもなるのであって、融通無碍もいいが、融通がきかないことにもまた一得がある。
知恵の幅
どんなに賢い人でも、神や仏ほどの知恵もなければ、どんなに愚かな人でも、ほんとうは犬猫に劣るというほどの人もいない。
いささかの賢さを誇り、些少の愚かさを卑下してみても、何ほどのことがあるのであろう。
小さな賢愚の中で、小さなおたがいの心を乱すまい。
まねる
人もまたみなちがう。柿のごとく梅のごとく、人それぞれに、人それぞれの特質があるのである。大事なことは、自分のその特質を、はっきり自覚認識していることである。
モデリングといって、目指す人をそのまんま真似することを推奨する人が多いなか、自分の特質を知ることが大事と言っている。
でも、まだまだ駆け出しの状態なら、そのまんま真似することも大事ではないかと思う。そうじゃないと、道を進めないのではないか。
わけ入れば
長い人類の歴史は、時に曲折はあったとしても、こうしておおむね進歩発展の一路を辿ってきた。今後もまたかぎりなく発展してゆくにちがいない。人間は本当に偉大なものである。
われわれもまた、この人間の歴史の一コマをになっている。
だからこそ、どんなことにも、もうこれでいいのだ、もうこれでおしまいだ、などと安易に考えないで、わけ入れば思わぬ道もあるという思いで、日々ひたすらな歩みを進めてゆきたいと思うのである。
談笑のうちに
口角アワをとばし、腕をまくらんばかりの大議論しながら、一向にものごとが進まないのは、この悪い自動車のようにどうもあまり感心した姿ではない。やっぱりよい自動車のように、最小限必要な議論に止め、それも談笑のうちにスムーズに運んでゆきたいものである。それでこそ議論がほんとうに世の中の繁栄に役立つことになるのであろう。
談笑のうちに、というのはいい表現だと思うし、そうありたいと思う。ただ、いい車にあこがれるあまりに、言うべきことを言わない、ということになる恐れはないのだろうか、と思う。
ただ、空気を読んですすめていく、というだけになってしまわないかが心配。
談笑で終わるかどうかは結果論で、相当力がある人ができることで、そうでない人はやはり不器用にでも伝えないとならないのではないだろうか。
スポンサーリンク
求めずして
手を合わすという姿は、ほんとうは神仏の前に己を正して、みずからのあやまちをよりすくなくすることを心に期すためである。頼むのではない。求めるのではない。求めずして、自らを正す姿が、手を合わす真の敬虔な姿だと言えよう。
ダムの心得
ゆとりをもって適時適切に放出する。人間の知恵の進歩であろう。
川にダムが必要なように、暮らしにもダムがほしい。物心ともにダムがほしい。ダラダラと流れっ放し、使いっ放しの暮らしでは、まことに知恵のない話。
商売の上にも、事業の経営の上にも、このダムの心得がぜひほしい。
稲盛和夫さんの「生き方」に松下さんの話として、このダムの考え方が出ていた。「道をひらく」においても最後から2番目という位置に登場するので、松下さんは相当この考え方を重視しているんだと思った。
経営においてダムとはなんだろう。キャッシュをためておくことか。何事にもバッファを設けることか。なんだろう。
「物心ともにダムがほしい」とあるので、心にもあったほうがいいのか。心のダムというのはどういうことだろう。
要約は以下で。
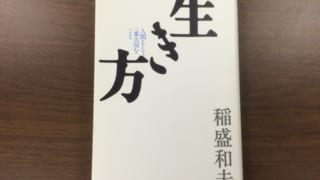
電子書籍とオーディオブックはある?
電子書籍はKindleと楽天KOBOで出ています。
本とオーディオブックが一体になたものもあります。ただ、こちらは続編は含まれていないようです。
Twitterでもビジネスに役立つ情報を発信しています。フォロー頂けたら嬉しいです。